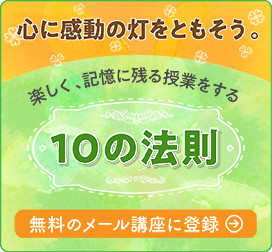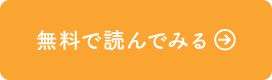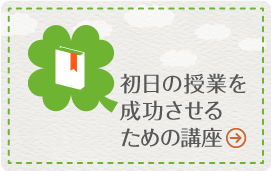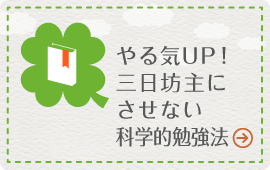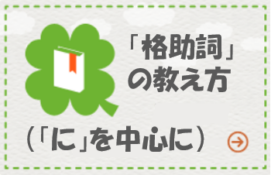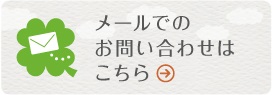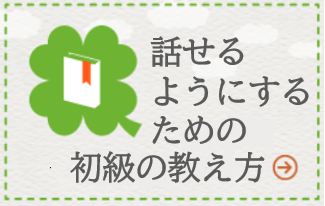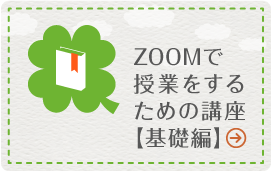日本語廃止論・漢字廃止論
日本語廃止論
何とも物騒な表題です。
この表題のように、
日本語が廃止されてしまったら、
日本語教師としては死活問題です。
この論は
開国を迫られた江戸時代の終わりごろから
明治時代にかけて、幾度も浮上しています。
有名なところでは
日本の初代文部大臣、森有礼氏が
日本語を廃止し、英語を公用語にしよう
と提案しました。
また、
小説の神様とも言われる作家の
志賀直哉氏は
「日本語をやめて、フランス語を
公用語にしたらどうか」
と意見を述べています。
(1946年『改造』4月号)
彼らが
こうした説を提唱した(書いた)ことは
事実ですが、
もしかしたら、現代のように
過激な個所だけが切り取られただけで、
本心からそう思っていたのかは
定かではありません。
(しかしながら、様々な本を読んでみると、
どうも本心のようです……。ただし、
日本という国の
将来を憂えてのことですが……)
このような『日本語廃止論』の出現は
日本語教育に携わっている者にとっては
ちょっと、いえ、かなり切なくなります。
漢字廃止論
『日本語廃止論』とまではいかなくとも、
『漢字廃止論』が巻き起こったことも、
今までに少なくとも大きなうねりが2度ほど
(否、もっと多いかもしれません)
あったようです。
日本の近代郵便制度創設の立役者でもある
「日本近代郵便の父」とも呼ばれている、
前島密(ひそか)氏が
初期のうねりを巻き起こした一人です。
前島密氏は
江戸幕府の最後の将軍、徳川慶喜氏に
漢字を廃止するように具申しています。
(その趣旨は
欧米から技術を学ぶのに、
漢字がその妨げになっており、
日本語は
「ひらがなとカタカナ」だけで充分である、
ということのようです)
まあ、漢字の勉強は
時間がとてもかかります。
欧米列強に追いつかなければと、
焦りに焦っていた時代です。
漢字の学びに時間を割くより、
その時間で他の技術を習得したほうが良い、
というその焦燥感は
当時の歴史的背景を考えれば、
わかるような気がします。
そして
時は立ち……
GHQの漢字廃止の勧め
次のうねりの『漢字廃止論』は
アメリカ軍中心の組織、GHQの提案から
起こりました。
GHQとは
第二次世界大戦後、日本を占領統治していた
連合国軍最高司令官(マッカーサー元帥)の
総司令部のことです。
正式名称は
「General Headquarters,
the Suprene Commander for
the Allied Powers」です。
当時、GHQの要請でアメリカから
「アメリカ教育使節団」
(大学の学長、教授、教育行政官などの27名)
が日本に派遣されてきました。
彼らは1946年に
「アメリカ教育使節団報告書」を
発表しています。
アメリカ教育使節団報告書
1946年に発表された
アメリカ教育使節団の報告書には
「歴史的事実、教育、言語分析の観点から見て、
本使節団としては
いずれ漢字は一般的書き言葉としては
全廃され、音標システムが
採用されるべきであると信じる」
とあります。
使節団が漢字廃止論を具申した背景
アメリカ教育使節団は
英語の、アルファベットのような表音文字の方が
漢字のような表意文字よりも、優れている、
と考えていました。
そこで、
漢字の勉強は時間の無駄であり、
その時間を数学や英語の学習に使うべきだと
考えたようです。
使節団は
難しい漢字のせいで、日本人の識字率が低いことを
目で見える形で証明しようとしました。
その手段として、
1948年8月、全国調査を開始します。
使節団は
日本全国から老若男女17000人を
無作為に選び出しました。
その人々に
漢字の理解度を確かめる(漢字)テストを
実施したのです。
90点満点(一問一点)のテストの平均点は
78.3点だったそうです。
アメリカ教育使節団としては
「日本では
こんなに難しい文字を使っているのだから、
読み書きができない人が多いに違いない」と
予想していました。
ところが、
正解がゼロの人は2%程度だったそうです。
この結果は使節団の想定とは正反対で、
(彼らはこの数字を見て、非常に驚いたそうです)
トレイナー(Joseph C. Trainor)氏は、
以下のような見解を述べました。
『結果は、
日本人の読解能力に偏見を抱いていた
多くの者にとって、
驚くべき困惑の種となるものであった。
何の公的な教育も受けていない人達のグループ
を別にすれば、
年齢・学歴・職歴そのほかの区分を問わず、
あらゆる日本人が
新聞に普通出て来る記事を
「読み、書き、理解する能力」
を持っていた。
テストの成績は
学歴と年齢により異なっていたが、
新聞記事を読む能力に関する限り、
日本人は躊躇なく
リテラシー「読み書きの能力(識字)」があると言えた』
結局、使節団の考え方は
的を外れていたということで、
漢字を廃止する意見書は
取り下げられたそうです。
(今考えると
合理的な判断を下してもらって、
本当に良かったと思います。
もし、
漢字が廃止されていたらと思うと、
恐ろしくなります)
ちなみに
英語のアルファベットは26文字ですが、
1950年のアメリカの識字率は
83%ぐらいだったと
とある言語学者が書いていました。
(その数字の出どころは記載されていませんでした)
その言語学者によると
2024年の調査では
アメリカの人口の21%は
社会人として適切に働くのに必要な
読み書きのスキルがないという
統計結果が出た、と言っています。
(数字の出どころの記載なし)
まあ、アメリカという国の
多種多様な人が集まり、暮らしているという
背景を考えると、
そうなるだろうなあ、
と合点がいきます。
正式な調査はありませんが、
日本の今の識字率は
100%に近いと言われています。
しかし、日本でも、
努力をしていかなければ、
あらゆる人が日本語の「読み・書き」が
できるようにはならないでしょう。
日本語ができなければ、
日本で暮らしていくのに
困難が伴います。
日本で暮らす誰もが
日本語が
使えるようになれるといいですね。
最後に
これからの日本で
『日本語廃止論』
『漢字廃止論』
が再び浮上してくる、ということが
あるのでしょうか・・・?
日本が八方ふさがり的な状況に陥った時?
そうならないことを願うばかりです。
日本語にとって
漢字はとても大切です。
ひらがなも、カタカナも、同様に大切です。
「にわにはにわにわとりがいる」
こうした一瞬見ただけでは
何を言っているのか、わからない文も、
漢字仮名交じり文で書けば、
「庭には二羽ニワトリがいる」
瞬時に意味が分かります。
これこそ、日本語の文字の素晴らしさです。
日本語教育に携わる者としては、
漢字が消滅しないよう、
見守っていきたいですね。
ではではニゴでした。